ランニングを続けていると筋肉が落ちるって本当?
そんな疑問を抱えて「ランニング筋肉 落ちる」と検索してきた方は少なくないはずです。
特に筋トレとランニングを並行している方や、健康やダイエットを目的に走っている方にとって、筋肉が減るのは避けたい問題です。
一部では「それは嘘」と言われることもありますが、実際には運動の強度や時間、栄養状態によって筋肉への影響は大きく変わります。
本記事では、論文などの科学的根拠をもとに、筋肉が落ちる理由や落ちやすい箇所、特に上半身の筋肉が落ちる原因についても詳しく解説します。
また、ランニングマシン使用時の注意点、知恵袋で見られるリアルな声、女性が筋肉をつけるケースや、筋肉を落とさない有酸素運動の時間設定、プロテインを活用した対策まで、実践的に役立つ内容をまとめました。
筋トレとランニングで筋肉が落ちるといった悩みを解消したい方に向けて、今すぐ活かせるヒントをお届けします。
■本記事のポイント
- ランニングで筋肉が落ちる仕組みとその理由
- 筋肉が落ちやすい部位や運動の時間の目安
- 上半身の筋肉減少を防ぐ具体的な方法
- プロテインや筋トレなどの効果的な対策方法
ランニングで筋肉が落ちるのは本当か?

ランニングを始めたばかりの方や、健康維持やダイエットを目的に走っている方の中には、「ランニングを続けると筋肉が減ってしまうのでは?」と不安に感じている人も少なくありません。
特に、筋トレと並行してボディメイクを意識している場合、この疑問は見過ごせない問題です。
実際、ネット上ではランニングで筋肉が落ちるという情報が多く見られますが、それは本当なのでしょうか?ここでは、このテーマを正しく理解するために、よくある誤解や科学的な視点からその実態を紐解いていきます。
ランニングで筋肉が落ちるは嘘なのか?
「ランニングをすると筋肉が落ちる」という情報は一見すると極端に感じられるかもしれませんが、完全に嘘とは言い切れません。
正しくは、「状況によって筋肉が落ちる可能性がある」というのが事実です。
つまり、ランニングの頻度や距離、食事内容、筋トレとの組み合わせによって、筋肉への影響は大きく変わります。
たとえば、1回30分程度の軽いランニングを週に2から3回行う程度であれば、筋肉が目に見えて減るようなことはほとんどありません。
むしろ、運動不足の人であれば、下半身の筋肉が適度に発達することもあります。
一方で、1時間を超える長距離走や10km以上のランニングを毎日続けている場合、筋肉が分解されてしまうケースも見られます。
これは体がエネルギー不足になったとき、脂肪だけでなく筋肉も分解してエネルギーとして利用しようとするからです。
とくに、糖質や脂質の摂取が足りないまま走ると、その傾向が強くなります。
このように、「ランニングで筋肉が落ちるかどうか」は、本人の体質や運動経験、食生活、トレーニング内容によって変わるため、すべての人に当てはまるとは限りません。
単純に「ランニング=筋肉が落ちる」と考えるのではなく、前提条件をきちんと理解したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
筋肉が落ちる理由を論文から解説

ランニングによって筋肉が減少する可能性がある理由は、主に「エネルギー源の枯渇」と「運動の種類」に起因します。
いくつかのスポーツ生理学の研究でも、長時間の有酸素運動が筋肉量に与える影響が報告されています。
まず、体はエネルギーとして最初に糖質(グリコーゲン)を使い、次に脂肪を使います。
そして長時間のランニングなどで糖質と脂肪が不足してくると、筋肉を構成するタンパク質(アミノ酸)を分解してエネルギーに変える「糖新生」が起こることが知られています。
これが筋肉が落ちる直接的な原因のひとつです。
また、2020年に発表された一部の運動生理学の論文では、長時間にわたる有酸素運動によって筋タンパク質の分解(MPB)が促進されることが確認されています。
筋肉を維持するためには、この分解と合成(MPS)のバランスが重要ですが、有酸素運動だけを続けていると、分解が上回ってしまう可能性があるのです。
さらに、筋肉には「速筋」と「遅筋」があり、ランニングのような持久運動では主に遅筋が使われます。
速筋は大きく力強い動きを担う筋肉ですが、使われないままでいると萎縮してしまう傾向にあります。
そのため、特に速筋の割合が高い人や筋トレをしていた人は、ランニングによって筋肉量が減るリスクが高まります。
これらの論点から見ても、ランニングが筋肉に与える影響は科学的にも明確に示されていることがわかります。
ただし、それを防ぐ方法も多く存在するため、正しい知識を持って運動することが大切です。
筋肉が落ちやすい箇所とは?
ランニングによって筋肉が落ちやすい部位にはいくつかの特徴があります。
特に、上半身の筋肉や太くて強い速筋繊維を多く含む部位が影響を受けやすいとされています。
まず、ランニングでは下半身の筋肉、特に大腿四頭筋やハムストリング、ふくらはぎなどが繰り返し使われるため、これらの部位に関しては筋肉が維持または発達する可能性があります。
ただし、長時間・高頻度で走る場合は、エネルギーの消費量が多くなるため、たとえ使っている部位でも筋分解が起こるリスクは無視できません。
一方で、上半身の筋肉、とくに胸筋や広背筋、肩回りの筋肉はランニング中にはほとんど使われません。
そのため、筋トレを並行して行っていない場合、これらの筋肉は使われずに徐々に減少していく可能性があります。
また、ランニングフォームが崩れていると、体幹(腹筋や背筋)への負荷も減少するため、これらの部位も衰えやすくなります。
さらに、日常的に筋トレをしていた人がランニングを取り入れた際に、筋肉量の変化を感じやすいのもこのような部位です。
特にボディビルやパワー系スポーツで発達した速筋は、持久運動にあまり適していないため、刺激が少ない状態が続くと縮小していきます。
このように、ランニングによって落ちやすい筋肉の部位は、主に「使っていない場所」や「速筋繊維が多い部分」です。
トレーニングのバランスを見直し、定期的に筋トレや体幹トレーニングを取り入れることが、筋肉減少の予防には欠かせません。
上半身の筋肉が落ちる理由
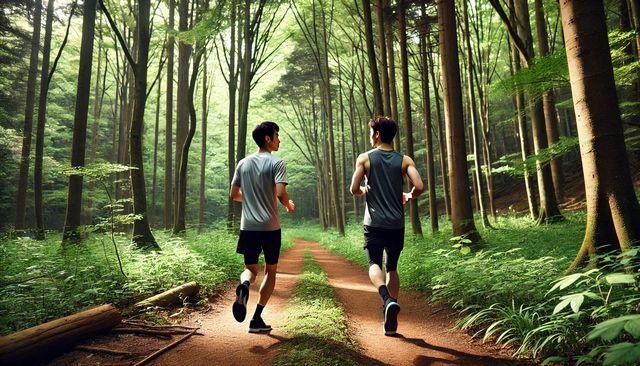
ランニングは基本的に下半身を中心に使う運動であり、上半身の筋肉にはあまり刺激が入りません。
これが、上半身の筋肉が落ちやすくなる大きな原因の一つです。
特に胸や背中、腕といった部位はランニング中にほとんど動かさないため、筋肉への負荷が少なく、維持するための刺激が足りなくなってしまいます。
また、ランニングを長時間行うことで、体はエネルギーを効率よく使おうとします。
糖質や脂質の消費が進むと、筋肉を分解してエネルギーに変える働きが起こります。
これがいわゆる「糖新生」という現象です。
とくに栄養状態が悪かったり、食事制限をしていたりすると、上半身の筋肉は分解の対象になりやすくなります。
さらに、筋肉には速筋と遅筋の2種類があり、ランニングでは主に持久力に優れた遅筋が使われます。
これに対し、上半身には瞬発力を発揮する速筋が多く含まれており、ランニング中にはほとんど使われないため、使わないまま時間が経てば自然と衰えていくことになります。
このような背景から、ランニングだけを続けていると、上半身の筋肉が徐々に落ちていくことがあるのです。
筋肉を維持したい場合は、ランニングとは別に上半身を刺激するトレーニングも並行して行う必要があります。
たとえば、腕立て伏せや懸垂、ベンチプレスなど、筋肉にしっかりと負荷をかける種目を定期的に取り入れることで、筋肉量を保つことができます。
筋肉が落ちる時間の目安とは?
どれくらいの時間ランニングをすると筋肉が落ちてしまうのか、これは気になるポイントかもしれません。
結論からいえば、30分程度のランニングであれば筋肉が著しく減る心配はほとんどありません。
筋肉の分解が起こりやすくなるのは、一般的に1時間以上、あるいは10kmを超える長距離を定期的に行った場合とされています。
ランニングを始めて最初の段階では、体は糖質と脂質を優先的に使います。
しかし、運動時間が長くなって糖質や脂質が枯渇してくると、体はアミノ酸、つまり筋肉を構成するタンパク質をエネルギー源として利用しはじめます。
これが筋肉量の減少につながる仕組みです。
特に注意が必要なのは、空腹状態でのランニングや、食事制限中に長時間走るケースです。
このような状況では、エネルギー不足を補おうとして筋肉の分解が早く進みます。
また、過度な有酸素運動を毎日のように行っている場合、筋肉の回復が間に合わず、結果的に筋肉量が減ってしまう可能性もあります。
目安としては、1回あたりのランニング時間を30分から45分以内、週に3から4回程度に抑えると、筋肉を落とさずに有酸素運動の効果を得ることができます。
運動前後にしっかりと栄養補給を行うこと、無酸素運動(筋トレ)との組み合わせを忘れないことも大切です。
ランニングマシンで筋肉は落ちるのか?

ランニングマシンを使っている方の中には、「この運動でも筋肉が落ちるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。
答えから言うと、ランニングマシンであっても状況次第では筋肉が落ちる可能性はあります。
ただし、マシンだからといって特別に筋肉への悪影響があるわけではありません。
屋外でのランニングとランニングマシンとの違いは、地面の不規則さや風の抵抗、勾配の変化があるかどうかという点です。
屋外では多少なりともバランスを取ったり、地形に合わせて筋肉を使ったりしますが、マシンは一定の動作を繰り返すため、刺激のバリエーションが少ないという特徴があります。
このことが、筋肉の維持に関して少しマイナスに働くこともあります。
ただし、それよりも重要なのは運動の「量」と「質」です。
例えば、傾斜をつけた状態でしっかりと負荷をかけたランニングであれば、屋外に負けない強度を得ることができます。
逆に、毎日1時間以上、傾斜のない一定スピードで長時間走るような使い方をしている場合、筋肉の分解リスクが高まる可能性はあります。
また、ランニングマシンでも上半身の筋肉は基本的に使われないため、屋外同様に筋トレとの併用が大切です。
筋肉を維持したいのであれば、週に数回、無酸素運動を取り入れ、栄養状態にも注意を払いましょう。
マシンか屋外かよりも、どのように運動を設計しているかが最も大切なのです。
ランニングで筋肉が落ちるのを防ぐ方法

ランニングは脂肪を燃やし、健康やダイエットに効果的な運動ですが、間違ったやり方を続けていると、せっかくの筋肉が落ちてしまうリスクがあります。
「引き締まった体を目指しているのに、筋肉が減ってしまった…」というのは避けたいものです。
そこでここでは、筋肉量をキープしながらランニングの効果を最大限に引き出すための、具体的で実践的な対策を詳しくご紹介します。
ランニングと筋トレの順番が重要
ランニングと筋トレを同じ日に行う場合、順番によって筋肉への影響やトレーニングの効果が大きく変わります。
一般的に推奨されているのは「筋トレを先に行い、その後にランニングをする」という流れです。
この順番は、筋肉の成長を促進しつつ脂肪の燃焼効率も高める、理にかなった組み合わせといえます。
先に筋トレを行うことで、筋肉に十分なエネルギーを使うことができ、効果的に筋繊維を刺激できます。
そして、筋トレによって血中の糖質(グリコーゲン)が減った状態で有酸素運動に入ると、体は脂肪を優先的に燃焼しやすくなります。
これが「アフターバーン効果」と呼ばれる現象にもつながり、トレーニング後の代謝が高まるというメリットも期待できます。
一方で、順番を逆にしてしまうと、ランニングで消費した後のエネルギーが不足しており、筋トレのパフォーマンスが低下しやすくなります。
さらに、筋肉の分解が進みやすくなってしまい、筋力アップや維持が難しくなることもあります。
もちろん、目的によって最適な順番は変わる場合がありますが、筋肉を落とさずに引き締まった身体を目指すのであれば、筋トレ→ランニングの順がベストといえるでしょう。
プロテインで筋肉を守る栄養補給のポイント

ランニングをしながら筋肉を維持したい場合、プロテインを活用した栄養補給は非常に効果的です。
筋肉は運動によってダメージを受けるため、その修復と成長には十分なタンパク質が欠かせません。
特にランニングのような有酸素運動では、筋肉の材料となるアミノ酸がエネルギーとして使われてしまうことがあり、これが筋肉の分解につながる要因となります。
プロテインは、効率的にタンパク質を補給できる手段として優れています。
運動前後や食事の補助として取り入れることで、体内のアミノ酸バランスを保ち、筋肉の分解を最小限に抑えることができます。
おすすめのタイミングは、運動30分前や運動直後です。
吸収の速いホエイプロテインであれば、トレーニング前後に摂ることで効果を最大限に引き出すことができます。
また、ランニングの前に何も食べずに走ると、エネルギー源が枯渇しやすくなり、体は筋肉を分解してタンパク質を補おうとします。
これを防ぐためにも、BCAAやEAAといったアミノ酸サプリメントを摂取するのも有効な手段です。
注意点として、プロテインの摂りすぎには気をつける必要があります。
あくまで補助食品として使い、食事からの栄養バランスを意識することが大切です。
バランスの良い食事と適切なプロテインの活用によって、ランニングをしながらでも筋肉の維持は十分可能です。
筋肉を落とさない有酸素運動の時間目安とは
筋肉を落とさずに有酸素運動を取り入れたい場合、運動時間の目安を意識することが重要です。
有酸素運動は脂肪燃焼に効果的な一方で、やり過ぎると筋肉の分解を引き起こしてしまう可能性があります。
特に、長時間のランニングや連日の過度な運動は、筋肉にとってマイナスに働きやすいので注意が必要です。
一般的に、筋肉を落とさずに脂肪を燃やしたい場合、1回あたりの有酸素運動は「30分から45分以内」にとどめるのが理想とされています。
また、週に3から4回の頻度であれば、筋肉への負担も抑えつつ、代謝の向上や体脂肪の減少といった効果が得られやすくなります。
一方、1時間を超えるランニングや10km以上の走行を日常的に行っていると、体がエネルギーを筋肉からも得ようとするため、筋肉量の低下を招きやすくなります。
特に、食事からのエネルギー摂取が足りていない状態では、その傾向が顕著になります。
こうしたリスクを避けるには、有酸素運動を行う際に強度と時間をコントロールすることが大切です。
たとえば、心拍数をやや上げる程度の軽めのランニングやウォーキングを、無理のない時間で継続するのが効果的です。
また、ランニングに加えて筋トレを週2から3回取り入れることで、筋肉の分解を抑えると同時に基礎代謝の向上にもつながります。
このように、有酸素運動の「やり方」次第で、筋肉を守りながら健康的な体づくりを進めることができるのです。
ランニングする女性でも筋肉はつくのか?

ランニングをすることで女性の体にも筋肉はつきます。
ただし、その筋肉のつき方は男性とは異なり、ボリュームが増すというよりは「引き締まる」「整う」といった形で現れることが一般的です。
特に女性の場合、筋肉を増やすために必要なホルモン(テストステロン)の分泌量が少ないため、よほどハードなトレーニングを行わない限り、筋肉がムキムキになるようなことはありません。
ランニングでは主に下半身の筋肉が使われます。
たとえば太ももやふくらはぎ、お尻の筋肉が繰り返し刺激を受けることで、余分な脂肪が落ち、引き締まったラインが出やすくなります。
さらに、正しいフォームで走ることができれば、体幹(腹筋・背筋)にも自然に負荷がかかり、姿勢改善にもつながります。
特に運動習慣がなかった女性がランニングを始めた場合、最初のうちは筋肉量の増加を感じやすいです。
運動によって筋肉が刺激され、基礎的な筋力が徐々に身についていくため、身体が軽くなったり、疲れにくくなったりといった変化も見られるでしょう。
このように、女性がランニングをすることで「筋肉質になる」というよりも、「健康的でメリハリのある体づくりができる」と考えるのが適切です。
筋肉を意識しすぎて運動を控えるのではなく、引き締まった身体を目指して上手に活用していくことをおすすめします。
知恵袋ではどう語られている?意見まとめ
「ランニングをすると筋肉が落ちるのか?」という疑問について、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトではさまざまな意見が投稿されています。
その内容を見てみると、実際にランニングを習慣にしている人たちの経験談や、専門的な知識を持つ方のコメントが混在しており、情報源としての一面もあります。
一部では「ランニングを続けていたら、上半身の筋肉が減ってしまった」といった声があり、特に筋トレと両立できていなかった人の間でこの傾向が見られます。
一方で、「走り始めてから脚が引き締まり、前よりも筋肉がついたように感じる」といった肯定的なコメントも多く見受けられます。
また、頻繁に出てくるアドバイスのひとつに「筋トレと併用することで、筋肉の減少は防げる」という意見があります。
これは運動生理学の観点からも正しく、単にランニングだけを続けるよりも、筋肉を維持・向上させるには無酸素運動との組み合わせが効果的だという考え方です。
加えて、食事の重要性に言及する声も多く、プロテインやアミノ酸の摂取を推奨する投稿も見られます。
「朝食前のランニングは筋肉が落ちやすいから、軽く栄養を入れてから走るべき」といった実用的なアドバイスもあり、実体験に基づいた信ぴょう性の高い情報が得られることもあります。
知恵袋の情報はあくまで個人の体験談が多いため、鵜呑みにするのではなく、信頼性の高い知識と照らし合わせながら取り入れることが大切です。
多様な視点から意見を集めることで、自分に合った運動スタイルを見つけやすくなるでしょう。
筋肉を落とさないための実践的対策

ランニングを日課にしている方が筋肉を落とさないためには、いくつかの具体的な対策を意識的に取り入れることが必要です。
筋肉の維持には運動の内容だけでなく、栄養・休養・運動のバランスが鍵を握っています。
まず1つ目の対策は、筋トレ(無酸素運動)との併用です。
有酸素運動だけを行うと筋肉の分解が進みやすいため、週に2から3回の筋トレを組み込むことで筋肉を保ちやすくなります。
特に上半身や体幹部の筋肉はランニング中に使われにくいため、ダンベル運動や自重トレーニングを通じて意識的に刺激を加えることが重要です。
2つ目は、ランニングの時間と強度を適切に調整することです。
筋肉を落としにくいランニングの時間目安は、1回30から45分程度、週3から4回を上限とするのが理想です。
さらに、心拍数を上げすぎないペースで走ることで、脂肪の燃焼を狙いつつ筋肉の分解を抑えることができます。
3つ目のポイントは、ランニング前後の栄養補給です。
特に空腹状態でのランニングは筋分解のリスクが高いため、BCAAや軽食などであらかじめエネルギーを補給しておくのが望ましいです。
また、運動後には速やかにプロテインや食事からタンパク質を補給し、筋肉の修復を促しましょう。
最後に、休養をしっかりと取ることも忘れてはいけません。
トレーニングの効果は休息中に現れるため、十分な睡眠やオフ日を設けることが、筋肉を守るうえでの重要な要素となります。
このように、日々のランニングを効果的に活かすためには、単に走るだけでなく、トレーニング全体の設計を見直すことが筋肉維持への第一歩になります。
【まとめ】ランニングで筋肉は落ちるを総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


