ランニング中に心拍数がすぐ上がってしまい、「自分だけ?」と不安になった経験はありませんか?
特に150や160、さらに170から180といった高い数値が続くと、運動強度が適切なのか気になるところです。
「ランニング 心拍数 下げたい」と検索したあなたは、きっともっと楽に、効率よく走りたいと考えているはずです。
この記事では、心拍数が高すぎることで起こるリスクや、すぐ上がる原因、年齢による平均値や目安、心拍数が上がりやすい人の特徴などを詳しく解説します。
また、マラソン選手の心拍数平均や、フルマラソンでの心拍管理とサブフォー達成のポイントにも触れながら、具体的な下げるトレーニング方法をご紹介。
時計やアプリを活用した管理術、脂肪燃焼やダイエットに役立つ心拍の使い方も網羅しています。
「感覚任せ」から一歩進んで、「データを味方にする」ランニングを始めてみませんか?
■本記事のポイント
- 心拍数150から180の意味と運動強度の目安
- 心拍数がすぐ上がる原因とその対策
- 年齢別の心拍数の平均と適切な管理方法
- 心拍数を下げるための具体的なトレーニングやアプリ活用法
ランニングで心拍数を下げたい人の基本対策

ランニング中に心拍数がすぐ上がってしまい、「このままで大丈夫なのか」と不安を感じたことはありませんか?心拍数は、体の負荷を表す大切な指標です。
特に健康やパフォーマンス向上を目指すなら、自分にとって適切な心拍数を理解し、上手にコントロールすることが重要です。
ここでは、心拍数を正しく把握し、無理なく下げていくための基本的な知識や方法をお伝えします。
まずは、心拍数の数値がどんな意味を持つのか、そして年齢や体調によってどのような目安があるのかを確認していきましょう。
心拍数150・160・170・180の意味と目安
ランニング中に表示される心拍数が「150」「160」「170」「180」と変動すると、それぞれの数値にどんな意味があるのか気になる方も多いでしょう。
これらの数値は、運動の強度や目的に応じた「トレーニングゾーン」として理解するとわかりやすくなります。
例えば、心拍数150は最大心拍数の60から70%にあたることが多く、これは脂肪燃焼や基礎持久力の向上に適したゾーンとされています。
この範囲では比較的楽に会話もできるため、有酸素運動として継続しやすく、初心者にも推奨される強度です。
160になると70から80%の運動強度に相当し、有酸素運動のパフォーマンス向上や、持久力を高めるトレーニングに適しています。
ある程度の息切れを感じるレベルで、一定時間の継続には慣れが必要です。
170を超えると80から90%の運動強度に入り、これは「無酸素運動」に近い領域です。
スピードを意識したペース走やインターバルトレーニングに使われ、筋力アップや心肺機能の強化に効果的ですが、初心者が無理をすると故障や過労のリスクもあるため注意が必要です。
180まで上がると、これは最大心拍数の90%以上とされ、レースのラストスパートや短距離走など瞬発力を求められる場面でよく見られる心拍数です。
この領域は心臓への負荷が非常に高く、長時間継続できるものではありません。
このように、心拍数の具体的な数値にはそれぞれ意味があり、どのゾーンを意識して走るかでトレーニングの効果が変わってきます。
目的に応じて、意図的に心拍ゾーンを調整することが、効率的なランニングに繋がるでしょう。
心拍数がすぐ上がる原因とは?

ランニングを始めてすぐに心拍数が急上昇してしまうと、ペースが合っていないのではと不安になる方もいるかもしれません。
実際、心拍数がすぐ上がってしまうのには、いくつかの原因があります。
まず考えられるのは「運動強度が高すぎる」ケースです。
スタート直後から速いペースで走り出すと、身体がまだ十分に温まっていない状態で急に負荷がかかり、心拍数が一気に跳ね上がることがあります。
これは特にウォーミングアップを省略してしまった場合に起こりやすいです。
また、「疲労の蓄積」や「睡眠不足」など、体調が万全でないときにも心拍数は上がりやすくなります。
これには、身体がストレス状態にあると自律神経が乱れ、心臓の働きに影響を及ぼすという背景があります。
さらに、前日の飲酒や高ストレス状態も影響するため、トレーニングの前後にしっかりとコンディションを整えることが大切です。
もうひとつ見落としがちなのが「気温や湿度の影響」です。
暑い日のランニングは、体温調整のためにより多くの血液が皮膚に流れる必要があり、その分だけ心臓が頻繁に血液を送り出そうとするため心拍数が高くなります。
これも身体にとっては自然な反応ですが、知らずにいつもと同じペースで走ると過剰な負荷になってしまいます。
このような要因が複合的に絡んで「心拍数がすぐ上がる」状態を引き起こします。
気になる方は、日々の体調や気象条件、ウォームアップの有無などを見直し、ゆっくりと走り始めることから始めてみてください。
心拍数が高すぎる状態のリスク
ランニング中の心拍数が常に高すぎる状態であると、知らないうちに身体に大きな負担をかけている可能性があります。
運動によって心拍数が上昇するのは自然なことですが、一定の上限を超える状態が続くと、さまざまなリスクが生じます。
最も大きなリスクは「心臓への負担が大きくなり過ぎる」ことです。
心臓も筋肉の一種であるため、過剰に働かせれば疲弊します。
長期間にわたり、頻繁に心拍数が最大値に近い状態でのトレーニングを行っていると、心筋の疲労や不整脈を引き起こす可能性があり、場合によっては命に関わるリスクもあります。
また、心拍数が高すぎる状態では「運動の効率が悪くなる」ことも見逃せません。
有酸素運動の効果を最大化するためには、脂肪をエネルギー源として使うことが重要ですが、心拍数が高すぎると体は糖質に頼りがちになります。
その結果、スタミナが持たずに早々に疲れてしまい、トレーニングの質も下がってしまいます。
さらに、常に高心拍でトレーニングしていると、リカバリーが追いつかなくなり「慢性的な疲労状態」に陥ることもあります。
このような状態では、免疫力も低下しやすく、風邪をひきやすくなったり、怪我のリスクも増加します。
適切な心拍ゾーンを維持しながらランニングを行うことで、安全かつ効率的に目標達成へ近づくことができます。
心拍数を計測できるデバイスを活用して、自分の心拍傾向を知ることは、健康的なランニングライフを送るための第一歩と言えるでしょう。
年齢別の心拍数平均と目安を知ろう

ランニングや運動時における心拍数の管理は、年齢によって大きく異なるという点を押さえておく必要があります。
年齢が上がるにつれて心拍数の上限は下がる傾向にあり、それに応じた「目安の心拍数」を理解することで、より安全で効果的なトレーニングが可能になります。
一般的に、「最大心拍数」は220から年齢を引いた数値でおおよその目安を知ることができます。
例えば30歳であれば、最大心拍数は「220-30=190拍/分」となります。
この計算式はあくまで目安ですが、多くの人にとって実用的な基準となります。
最大心拍数がわかれば、トレーニング目的に応じて適切な運動強度を決められます。
例えば、脂肪燃焼を目的とした有酸素運動であれば最大心拍数の60~70%程度、つまり30歳の人なら114~133拍/分の範囲が推奨されます。
一方で、心肺機能や筋力向上を狙う高強度のトレーニングであれば、80~90%(152~171拍/分)が目安になります。
また、年齢が上がると血管や心臓の柔軟性が低下しやすく、心拍数が上がりにくくなることもあります。
高齢者の場合は無理な高強度運動を避け、医師と相談のうえで適切な心拍数範囲内に抑えることが大切です。
このように、年齢別の心拍数の目安を理解することで、無理のないトレーニング計画を立てることができます。
過度な負荷を避けつつ、目的に合った強度で継続することが、健康的な運動習慣の基本です。
マラソン選手の心拍数の平均とは?
マラソン選手がトレーニングやレース中にどれほどの心拍数で走っているのかは、一般ランナーにとっても気になるポイントでしょう。
心拍数は個人差があるものの、マラソン選手の平均的な心拍数は、一般のランナーに比べて高い持久力と心肺能力を示す指標となります。
トップレベルのマラソン選手がフルマラソンを走る際には、最大心拍数の80~90%程度で走り続けることが多いとされています。
例えば、最大心拍数が190であれば、152~171拍/分の範囲で42.195kmを走るということになります。
一般の市民ランナーではこの心拍数を長時間キープするのは非常に困難ですが、プロ選手たちはそれを日常的に行っています。
これは、彼らが高い「LT値(乳酸性作業閾値)」や「VO2MAX(最大酸素摂取量)」を持っているからです。
これらの数値は、心拍数と密接に関係しており、トレーニングを積むことで心拍ゾーンの中でも高い強度を長く維持することが可能になります。
一方で、日常的なジョギングやリカバリーランの際には、プロ選手でも非常に低い心拍数(120前後)で走っているケースもあります。
これは、走力を維持しながら疲労を残さないようにするための重要な戦略です。
このように、マラソン選手は「高強度でも維持できる心拍ゾーン」と「低強度で効率よく回復する心拍ゾーン」の両方を使い分けています。
一般ランナーにとっても、この考え方は非常に参考になります。
高心拍の状態を目指すのではなく、自身の目標に応じた適切な心拍ゾーンを見つけることが、パフォーマンス向上への近道となるでしょう。
心拍数を測るためのおすすめ時計
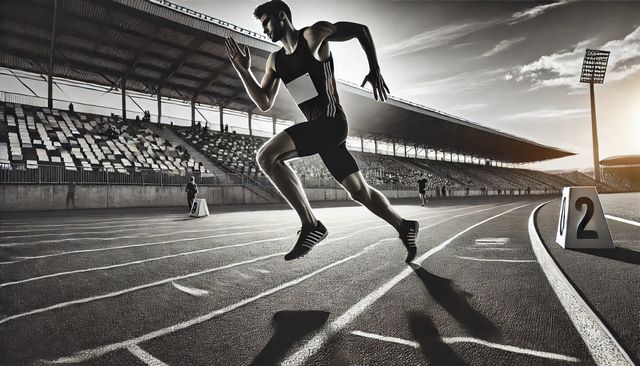
心拍数を正確に把握するためには、信頼できるツールの使用が欠かせません。
現在では多くのランナーがスマートウォッチやスポーツウォッチを活用しており、心拍トレーニングを行う上で「時計」は必要不可欠な存在になっています。
心拍数を測定できる時計には、大きく分けて2つのタイプがあります。
一つは「光学式センサー」が手首に内蔵されているタイプで、手軽に装着できるのが魅力です。
ランニング中にリアルタイムで心拍数を確認でき、スマートフォンのアプリと連携して詳細な記録を残すことも可能です。
もう一つは「胸部に装着する心拍センサー」とペアで使うタイプの時計です。
こちらは心電図に近い精度で測定できるため、より正確なデータが欲しい中上級者に向いています。
特にインターバル走やペース走など、心拍数の変動が激しい練習をする際には、この精度が大きな差を生み出します。
また、多くのモデルでは、心拍ゾーンの表示やアラート機能が搭載されており、設定したゾーンを超えた場合に知らせてくれるため、無理な運動を防ぐことができます。
加えて、VO2MAXの推定値やトレーニング負荷の分析機能を持つモデルもあり、心拍ベースのトレーニングに深みを加えてくれるでしょう。
ただし、どんなに高性能な時計であっても、装着方法が適切でないと正しい数値が出ません。
センサー部分がしっかりと肌に密着しているかを確認し、毎回同じ位置で装着するよう心がけると良いでしょう。
このように、心拍数を管理するための時計は、ランナーのレベルに関係なく非常に便利なツールです。
目的や予算に応じて自分に合ったモデルを選ぶことで、より効果的なトレーニングが可能になります。
ランニングで心拍数を下げたい人向け対策法

心拍数が高くなりやすいと感じている方にとって、単にペースを落とすだけでは根本的な解決にはなりません。
実は、日頃のトレーニング内容やライフスタイル、そしてちょっとした工夫によって、心拍数を効率的にコントロールすることが可能です。
ここでは、心拍数を下げるための具体的なトレーニング方法や、役立つアプリの紹介、さらには心拍数が上がりやすい人に共通する特徴など、実践的な対策をご紹介します。
今の走りを一段階レベルアップさせたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
心拍数を下げるトレーニングの方法
心拍数をコントロールしながらランニングを楽しむには、意識的なトレーニングが欠かせません。
特に「すぐに心拍数が上がってしまう」「同じペースでも以前より息が上がる」という方は、心肺機能を鍛えるだけでなく、身体のエネルギー効率を高めるような方法を取り入れる必要があります。
効果的なのが「低強度・長時間のランニング」、いわゆる「ゾーン2トレーニング」です。
これは最大心拍数の60から70%の範囲を目安に、会話ができる程度のペースで長時間走るトレーニングを指します。
この強度の運動は、脂肪をエネルギー源とする能力を高め、心肺への負荷も適度に抑えられるため、継続しやすいのが特徴です。
結果として、徐々に「同じペースでも心拍数が上がりにくい身体」が作られていきます。
もう一つのアプローチは「鼻呼吸ラン」です。
意識して鼻だけで呼吸をしながら走ることで、呼吸が浅くなるのを防ぎ、酸素の取り込み効率が改善されます。
この方法は慣れるまでに時間がかかりますが、心拍数の上昇を抑える感覚を養ううえで非常に効果的です。
また、インターバル走やテンポ走のような高強度トレーニングを週に1から2回取り入れると、最大心拍数に近い強度に身体を慣らすことができます。
ただし、このような練習を頻繁に行うと逆に疲労が蓄積しやすく、心拍数が上がりやすい状態になってしまうため、必ずリカバリー期間を設けることが重要です。
このように、日々のジョギングと高強度トレーニングのバランスを取りながら、継続的に心拍数を管理していくことが、結果的に「心拍数が上がりにくいランナー体質」への近道となるでしょう。
心拍数を管理できるおすすめアプリ

心拍数を意識したランニングをする際、スマートフォンアプリは非常に便利なツールです。
現在では、心拍ゾーンの把握、データの可視化、トレーニングの自動記録など、さまざまな機能を持つアプリが多く提供されています。
これらを活用すれば、無理のない範囲で心拍数を下げるトレーニングがしやすくなります。
代表的なアプリのひとつが「Garmin Connect」です。
Garminのスマートウォッチと連動することで、リアルタイムの心拍数やトレーニング効果、VO2MAXなどの指標を自動で記録してくれます。
ゾーンごとの運動時間も確認できるため、トレーニング後の振り返りにも役立ちます。
もう一つおすすめなのが「Strava」です。
主にランナーやサイクリストに人気のアプリですが、心拍数のトラッキング機能も充実しています。
他のユーザーとデータを共有し合えるため、仲間と目標を共有しながらモチベーションを保つことができます。
外部センサーとも連携できるので、正確な心拍数の取得が可能です。
さらに、Apple Watchを使用している方であれば「Apple ヘルスケア」も有効です。
日常の心拍数変動や運動時のデータを自動で保存し、心拍数の傾向をグラフで把握できます。
アプリ内で異常な変動があれば通知してくれる機能もあるため、健康管理の面でも安心です。
これらのアプリは基本的に無料で使用できますが、より高度な分析機能を使いたい場合は有料プランへの切り替えも検討してみてください。
まずは使いやすいアプリから始めて、心拍数の変化を日々記録していくことが、トレーニング精度の向上につながります。
心拍数が上がりやすい人の特徴とは?
ランニングや軽い運動を始めた途端に心拍数が急に上がってしまう人には、いくつか共通する特徴が見られます。
これらを把握しておくことで、自分の心拍傾向を理解し、より適切なトレーニング方法を選ぶことができるようになります。
まず最も多いのが「運動不足や初心者」の方です。
これまで運動習慣がなかった場合、心肺機能がまだ十分に発達しておらず、少しの負荷でも心拍数が跳ね上がりやすくなります。
特に早いペースでのスタートや、アップをせずに本練習に入ると、心臓に急激な負荷がかかりやすくなります。
また「ストレスが多い人」も、心拍数が上がりやすい傾向があります。
精神的な緊張や不安が続いていると、自律神経が乱れ、交感神経が優位になりやすくなります。
これにより、安静時でも心拍数が高めになり、運動時にはさらに急激に上昇することがあります。
他にも「睡眠不足」や「脱水状態」も見逃せない要因です。
睡眠によって身体は回復と調整を行いますが、それが不十分だと心臓の働きにも影響します。
また水分不足になると、血液の流れが悪くなり、それを補おうと心臓がより早く動くため、心拍数が上がります。
体質的な要因として、「筋肉量が少ない」または「基礎代謝が低い」ことも関係しています。
筋肉は酸素を消費する組織でもあるため、筋力が少ないと酸素運搬効率が悪くなり、結果的に心拍数が高まりやすくなります。
このような特徴を持っている方は、まずは生活習慣の改善や運動前の準備運動から意識してみましょう。
無理に速く走ろうとするのではなく、ゆっくりとしたペースで身体を慣らすことが、心拍数の安定につながります。
フルマラソンで心拍数とサブフォー達成

フルマラソンにおいて「サブフォー(4時間以内での完走)」を目指すランナーにとって、心拍数の管理は非常に重要なポイントです。
ただ闇雲に走るだけではなく、心拍数を基準にしたペース管理ができれば、体力の無駄遣いを防ぎ、後半に失速するリスクも減らすことができます。
サブフォーを目指す際のペースは、おおよそ5分40秒から5分50秒/km程度になります。
このペースで42.195kmを走り切るには、持久力だけでなく、心拍数を無理のない範囲でコントロールし続ける力が必要です。
目安としては、最大心拍数の70から80%、ゾーン2からゾーン3の間に収まる範囲が理想とされます。
たとえば最大心拍数が190の方であれば、心拍数133から152拍/分がこのゾーンに該当します。
この範囲を維持することで、脂肪を主なエネルギー源とする効率的なランが可能となり、グリコーゲンの消耗を抑えながら長時間のランニングが実現できます。
逆に心拍数がゾーン4(最大心拍数の80から90%)に入り続けると、エネルギーの消耗が激しくなり、30km以降に失速する「マラソンの壁」に直面しやすくなります。
日頃のトレーニングでは、レースペースに近い心拍ゾーンを確認しながら走ることが大切です。
また、30km走やロングジョグの中で、目標とするペースと心拍のバランスを意識しておくと、レース本番でも焦らず対応できます。
このように、フルマラソンでのサブフォー達成には、単なるペース管理だけでなく、心拍数という「体からのサイン」にも耳を傾けることが欠かせません。
脂肪燃焼とダイエットに効く心拍管理
脂肪を効率よく燃焼させたい、ダイエットのためにランニングを始めたという方にとって、心拍数を意識することは非常に効果的です。
適切な心拍ゾーンを保つことで、無理なく脂肪燃焼効率を最大限に引き出すことができます。
一般的に、脂肪がもっとも燃えやすい心拍数の範囲は「最大心拍数の60から70%」とされています。
これは「脂肪燃焼ゾーン」とも呼ばれ、ウォーキングや軽いジョギングなど、やや楽に感じる運動強度です。
このゾーンでは身体が主に脂肪をエネルギー源として利用し、持続的に運動を続けやすいため、ダイエットに非常に向いています。
例えば、30歳の方の最大心拍数はおおよそ190拍/分なので、その60から70%は114から133拍/分になります。
この範囲内でランニングや速歩きを行うことで、筋肉や心臓に過度な負担をかけずに、脂肪を燃焼しやすい状態を維持できます。
一方、これを超えて心拍数が上がり過ぎてしまうと、身体は糖質を優先的にエネルギー源とするようになります。
これは短時間で高い運動効果を得るには良いのですが、長く続けるには不向きであり、結果的に継続性が落ちやすくなってしまいます。
また、脂肪燃焼を目的とする場合、運動時間は最低でも20から30分以上が目安です。
心拍ゾーンを安定させた状態でこの時間を超えることで、体脂肪の分解が促進されやすくなります。
さらに継続することで基礎代謝も上がり、痩せやすい体質に近づいていきます。
つまり、ダイエット目的のランニングでは、運動の強さだけでなく「心拍数の質」に目を向けることが、無理なく成果を出すための鍵となります。
効果的な低強度ランで心拍を整える

心拍数を整えるには、高強度なトレーニングよりも「低強度のランニング」を継続的に行うことが大きな効果を発揮します。
このアプローチは、特に初心者や心拍数が上がりやすい体質の人に適しており、身体への負荷を最小限に抑えながら、心肺機能や血流の改善に働きかけます。
低強度ランとは、会話ができる程度のペースで、最大心拍数の50から70%程度に収まるような運動を指します。
この運動ゾーンでは、身体が酸素をしっかり取り込みながらエネルギーを作り出しているため、無理なく長時間続けることが可能です。
その結果、心臓の1回あたりの拍出量が増え、徐々に「低い心拍で効率的に走れる体」へと変化していきます。
このようなトレーニングは「心拍トレーニングの土台」とも呼ばれ、基礎的な持久力や代謝機能の強化に非常に効果的です。
例えば、週に2から3回、30分から60分程度の低強度ランを取り入れることで、運動中の心拍数の上昇を抑える力が身についてきます。
加えて、低強度ランは「疲労抜きジョグ」としての役割も果たします。
ハードな練習をした翌日に軽く走ることで、筋肉や血管の回復が促進され、心拍数の安定にもつながります。
ただし、低強度ランでもフォームが崩れていたり、呼吸が乱れていたりすると効果が半減してしまいます。
できるだけリラックスした姿勢で、鼻呼吸を意識しながら走ることで、さらに心拍数のコントロールがしやすくなります。
このように、低強度ランは即効性のある方法ではありませんが、確実に心拍の反応を整えるトレーニングです。
継続することで、無理のないペースで走れるようになり、結果としてパフォーマンスの底上げにもつながっていきます。
【まとめ】ランニングで心拍数を下げたいを総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。

